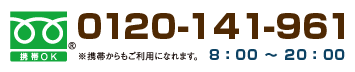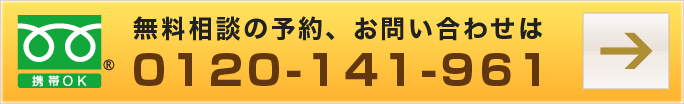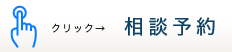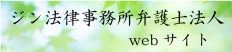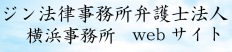アコム貸付停止措置と過払い金
神戸地方裁判所平成28年3月10日判決
アコム貸付停止措置と過払い金
アコムの過払い金で、貸付停止措置から消滅時効が進行するとの主張を否定した事例です。
取引が終了していないのに、返済期間だけが続いているケースで、このような貸付停止から10年で過払い金も消滅時効になるとの主張が多くされています。
返済が長期間続いているような取引履歴の場合には、この主張へ対抗できるようにしておきましょう。
判決では、アコムからの消滅時効の主張を否定し、過払い金約197万円を支払うように命じています。
消滅時効の成否についての判断枠組み
過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が行われた場合の過払金返還請求権の消滅時効について判例(最一小判平成21年1月22日民集63巻1号247頁)は次のとおり判示しており、本件における消滅時効の成否はこれに従って判断すべきである。
すなわち、「過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金に係る不当利得返還請求権(「過払金返還請求権」)を行使することは通常想定されていないものというべきである。
したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することをせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうする
と、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。」という内容です。
このような判断枠組みからして、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当であると指摘しています。
過払い金の時効の例外となる特別な事情とはどの程度のものが必要か、その枠組を示してくれています。
アコムとの取引内容
本件取引が終了したのは借主が最後の弁済をした平成16年6月6日であり、本件訴えの提起は平成26年6月5日であるから、判例にいう特段の事情がない限り、10年の消滅時効期間が経過する前に訴えが提起されたことになり、消滅時効は完成していないという前提を確認。
この特段の事情については、判例が「上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情」としていることに注意すべきであると指摘。
すなわちまず、過払金充当合意の内容と異なる合意が存在すれば、ここにいう特段の事情があることになります。
しかし本件において当該合意が存在したことは主張も立証もされていない。
合意はありませんでした。
過払い金が時効になる特段の事情とは
次に、当該合意は例示として挙げられているものであるから、これが存在しなくても特段の事情があるといえる場合のあることは明らかであるが、判例があえて例示として挙げているからには、特段の事情があるといえるためには、当該
合意の存在に準じる事情がなければならないと解されると指摘。
本件で問題となるのはそのような事情の有無であるとしています。
合意の存在に準じる事情である以上、借主の認識が問題となるというべきであり、過払金充当合意の内容等を勘案すると、そのような事情があるといえるためには、少なくとも、「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった」ことを借主が明確に認識することが必要であると解されるとしました。
いいかえると、基本契約に基づく新たな融資を申し込んでも貸主によってそれが拒絶される状況にあるということを借主が明確に認識することが必要であるというべきであるとしています。
過払い金と貸付停止措置の事情
アコムは平成13年2月15日に控訴人に対する貸付停止措置(本件基本契約に基づいて新たな融資をすることを停止する措置)をとったとし、これが特段の事情にあたると主張。
この主張の根拠としてアコムの主張する事実は次のとおり。
①アコムが平成13年2月15日に借主の与信歴データの「期待CL」値を50から0にしたこと
②
借主が平成8年3月19日以降アコムとの間でATMによる取引のみを行っていたことを前提として、平成13年2月15日の前後で借主のために表示されるATMの取引両面の表示が変更になったこと、すなわち「ご返済」「ご融資」「残高照会」「暗証番号の変更」「極度額等の変更申込」「取消」の各ボタンのうち「ご融資」のボタンと「極度額等の変更申込」のボタンが表示されなくなったこと
③ 平成13年2月15日の前後でATMが発行する利用明細書の「利用可能額」欄の表示が変更になったこと、すなわちそれまで表示されていた具体的な金額が表示されなくなり「*」のみが表示されるようになったこと
④ 借主は平成11年7月から平成13年2月5日まではほぼ毎月1回借入れと弁済を同じ日に行っていたが、同年3月からは毎月1回弁済のみを行ったこと
このような主張確認をして、これが特段の事情になるかを検討していくことになります。
アコムの貸付停止措置では時効にならない
このうち①は貸主内部の事情であり、借主のあずかり知らないことであるから、その認識に影響せず、特段の事情になりえないとしています。
②は、借主が利用したATMの取引両面の表示がいかなるものであったのかは証拠上明らかでないと指摘。
貸主の提出する証拠はサンプルにすぎず、借主が実際に利用したATMの取引画面が平成13年2月15日を境にして貸主の主張するように変更されたか否かは定かでない。仮にこの事実が認められたとしても、「ご融資」のボタンと「極度額等の変更申込」のボタンが表示されなくなったにすぎず、融資不可という意味を有する表示がされたわけではないから、新たな融資を申し込んでも拒絶される状況にあることを借主が明確に認識したとはいえないと確認しています。
③は、たしかにそのような事実があったと認められる。しかし「*」はそれだけでは意味のない記号であり、一般人は、そこに融資不可の意味がこめられていると理解することはできない。借主についても同様とみるほかないと指摘。
したがってこの事実だけでは、新たな融資を申し込んでも拒絶される状況にあることを借主が明確に認識したとはいえないとしました。
④も事実そのとおりである。しかし、継続的な金銭消費貸借取引を行う者が常に借入れと弁済を交互に繰り返すわけではなく、弁済のみを繰り返し行い、それが相当長期間に及ぶ場合があることは、当裁判所に顕著な事実であると指摘。したがって、④の事実だけでは、新たな融資を申し込んでも拒絶される状況にあることを借主が明確に認識していたと認定することはできないと結論付けています。。
過払い金の時効は成立していない
このように、①の事実は特段の事情になりえないし、②~④の事実は、いずれもそれのみでは特段の事情にならないと認定。
また②~④の事実をあわせてみても、やはり、新たな融資を申し込んでも拒絶される状況にあることを借主が明確に認識していたと認定するには不十分で、あるというべきであり、特段の事情にはならないと結論付けました。
以上によれば、本件取引について判例にいう特段の事情があるとはいえないから、借主の過払金返還請求権について消滅時効は完成していないとしています。
アコムの貸付停止措置への反論
あくまで、 最高裁平成21年1月22日判決では、過払い金取引の終了の時点とは異なる時点から消滅時効が進行を始
める場合を「上記内容と異なる特段の合意が存在するなど特段の事情がないかぎり」と判示しています。
特段の事情は「合意の存在」に準ずるものでなければならないはず。「合意の存在」に準ずる事情である以上、借主の認識を重視すべき。
借主側の認識が問題あるという場合には、この裁判例の利用により、有利な主張ができるでしょう。
過払い金請求の参考にしてみてください。