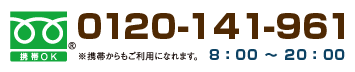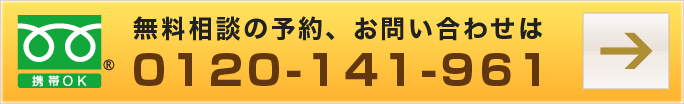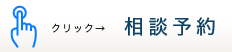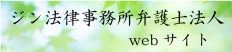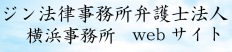約定過払い金と取引分断の判決
大阪簡裁令和元年6月4日判決
約定過払い金と取引の分断
被告アイフルとの間で、取引分断が争われた裁判例です。
第一取引最後の端数処理が、第二取引開始時にどのようにされていたかによって、一連計算が認められる可能性が高まります。
約定過払い金とは?
このケースでは、第一取引で約定過払い金が出ていました。
過払い金とは、通常は、契約で決められた約定利率が、利息制限法に違反しているため、これを引き直すことで発生するものです。
これが通常、過払い金と呼ばれるものです。
これに対し、約定過払い金とは何かというと、契約で決められた約定利率の利息で計算しても、過払いになっているものです。
どう考えても過払い金が認められるものです。
約定過払い金はなぜ発生するの?
このような約定過払い金が発生する理由は、払いすぎているからです。
なぜかというと、ATMや振込の関係です。
一部のATMで返済をする際に、1000円単位でしか処理ができなかったりします。
振込の場合も、同じように、1000円単位になってしまうことがあります。
最終返済をする際に、残債務が700円のところ、1000円を返済すると、300円が払い過ぎになります。
完済時に窓口等での処理をしていれば、このような約定過払い金はないのですが、機械の都合上、返済方法によって、このような約定過払い金が発生しているのです。
約定過払い金が発生する理由がこのようなものですので、通常、その金額は数百円です。
弁護士からの受任通知を送った段階で、このような約定過払い金が発生している場合、貸金業者も争えないので、数百円はすぐに返金していきます。
約定過払い金の処理
本件では、第一取引で約定過払い金276円が発生していました。
このうち200円がどうなったのかが争われたのですが、これは、第二取引の契約書に貼る印紙代として使われたと認定しています。
この点はアイフルの主張を認めています。
契約書には、額面200円の収入印紙が貼付されていました。
契約書の第9条には、原則として印紙代200円はカード会員(債務者)が負担すべきものとされていることから、約定過払金200円をもってこれに充当させたと考えるのが自然だと認定しました。
この点からも、アイフルは、第2契約締結時において、約定過払金の存在を認識していたと認定しています。
契約の一体性は?
第一取引では約定過払い金があり、そのまま第二取引が開始されていることから、借主は同一契約であると主張しましたが、これは否定されています。
第2契約は、第1契約の借入金債務が、約定年率による計算によって全額が弁済された(ただし、276円の過払状態)後に締結されたこと、新たに契約書が作成され、約定年率も借入限度額も異なることから、第1契約とは別個の契約であるとしています。
一連計算は?
契約が別でも、充当合意が認められれば、一連計算が採用されます。
第1取引において発生した過払金を第2契約における借入金債務に充当する旨の合意が存在したという借主の主張は認められたのでしょうか。
まず、重視されるのが空白期間。
本件取引1の終期(平成19年5月9日)から本件取引2の始期(平成21年5月26日)までの期間は、748日間であり、2年以上の空白期間がありました。
これは、本件取引1の期間が6か月間、本件取引2の期間が3か月間であることと比較して、相当な長期間であり、本件取引lと本件取引2の連続性を否定する事実と評価されます。
かなり、不利な取引内容です。
しかし、第1契約書は、本件取引1の終了後も借主に返還されておらず、約定過払金276円の返納手続もとられていませんでした。また、本件取引1で使用されていたATMカードについての失効手続もとられませんでした。
このような事実から、借主とアイフルとの間においては、本件取引1の終了後も、その後の取引を予定していたものと評価することもできるとしています。
ここで約定過払い金の評価
最高裁が充当合意を認める諸要素からすると、若干、不利な認定がされそうなケースです。
しかし、ここで、約定過払い金の処理が注目されます。
約定過払金276円のうち、200円については、第2契約締結の費用に充当され、残りの76円については、第2契約を開始した翌日に、第2契約の借入金債務に充当されている事実がありました。
ここから、約定過払金について第2契約の締結費用及び借入金債務に充当させる合意の存在が認められるとしています。
さらに、そうであれば、法定利率の引き直し計算によって発生した過払金についても、第2契約における借入金債務に充当する合意があったと認めるべきであると展開しています。
約定過払い金の処理から、過払い金充当合意を認定しています。
「第2契約に基づく取引を第1契約に基づく取引と一体のものとして取り扱う意思があったと認められ、本件取引1と
本件取引2は、長期にわたる空白期間を考慮しても、事実上1個の連続した貸付取引として、一連一体のものと評価するのが相当である。」
これにより、第一取引の過払い金の消滅時効を否定しています。
悪意の受益者該当性は?
アイフルは、悪意の受益者についても争ってきますが、ここは借主側が有利なところです。
「貸金業者が利息制限法所定の制限超過部分を債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定される。」
特段の事情も認められないとして、過払い利息も認めています。
約定過払い金があり、分断が争われている場合には、このような主張をしてみると良いでしょう。