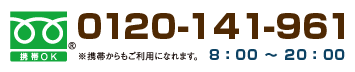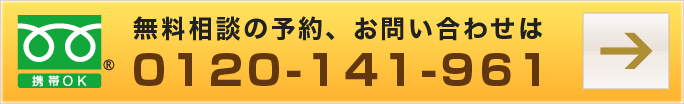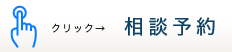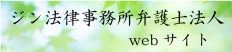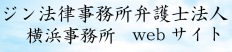債権譲渡と借り換えの過払金計算の判決
大阪高等裁判所令和元年8月28日判決
CFJの契約切り替え合意が和解になるか
CFJ合同会社に対する過払金請求で、過去の和解が問題になった裁判例です。
CFJが控訴人、借主が被控訴人となった事件です。
もともとがユニマットの取引でした。
大阪高等裁判所令和元年8月28日判決
CFJは、基本契約2の締結に先立つ平成15年1月1日に、ユニマットを吸収合併していたから、基本契約1の契約当事者として新たに基本契約2を締結したといえるが、同契約締結の際、借主から極度額借入契約書(兼告知書)の差入れを受けたのみで、改めて与・信審査を行った様子はうかがえないとしています。
まずは全体取引の基本契約の関係について認定しているものです。
そして、基本契約2の締結日に、同契約に基づく貸付金75万円の内66万2149円は現実の交付を伴うことなく本件取引1の残債務元本の弁済に充てる処理をする一方、同取引の未収利息2118円は弁済を受けずに残し、これを同日付けで本件取引2の未収利息として計上する処理をしていることからすれば、本件取引2は、本件取引1の借換えにすぎないものと評価するのが相当であって、本件取引1及び本件取引2は、不可分の1個の連続した取引であると評価するのが相当であるとしました。
計算方法や利息の処理方法から借り換えと同一、一体化を認定したものです。
CFJは、本件取引1が平成15年8月4日まで存続し、本件取引2と併存していたように主張するが、併存の根拠となる本件取引1の未収利息は、上記のとおり、本件取引2の開始当日に同取引の未収利息として計上する処理がCFJ自らによってされているから、この点に関するCFJの主張は採用できないと、別取引であるとの主張を排斥しました。
変更合意による過払い金放棄?
本件では、CFJと借主の間で作成された変更合意により、過払い金も放棄するような和解が成立したといえるかが争われました。
このような主張は、かなり強引に消費者金融からされることもありますが、裁判所は次のように排斥しています。
借主は、同通知書の内容について承諾するに当たり、CFJに対し、経済的困窮から、毎月の返済額の軽減のみをCFJに求めていて、CFJの主張する債務額を争っていたわけではなく、ましてや、過払金返還請求権を有する旨を主張していたわけではないものです。
他方、同通知書の1条には、「尚、原契約の借入利率が利息制限法第1条1項に規定する利率を超える場合、また遅延損害金の利率が利息制限法第4条1項に規定する利率を超える場合には、その超えた部分の利息又は遅延損害金については、支払う義務はありません。」との記載があるが、CFJは、借主の取引履歴を見直して、過払金が発生しているか否かを確認したことはなく、また、その検討を借主に促したことはありませんでした。
上記の事実からすれば、本件変更合意当時、当事者間にCFJが主張する本件取引における借入残債務の金額を含めその存在について争いがあったわけではなく、単に経済的に困窮した借主が、CFJが主張する同債務の存在を前提とし
て毎月の返済額(支払条件)の軽減を求めていたにすぎないと認められるし、その結果なされた本件変更合意も、CFJが主張する本件取引における借入残債務の存在を前提として、その弁済方法を取り決めたにすぎないものと認められるから、本件変更合意をすることで「当事者が互いに譲歩をし」たとも、また、「争いをやめることを約」したともいえないとして、CFJの主張を排斥しました。
CFJの過払い金額は?
過払い金放棄の合意もなく、一体取引となった場合の過払い金額については、どの程度になったのでしょうか。
利息制限法に基づく引き直し計算をすると、その計算結果は別紙計算書のとおりであって、CFJは、借主に対し、過払金として212万4553円(既発生の利息60万9274円を含む。)及びうち過払元金151万5279円に対する平成30年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払の不当利息債務を負っていることになるとしています。
原判決は相当であって、CFJによる本件控訴は理由がないから、これを棄却。
いわゆる過払い利息を含めて200万円以上の請求を認めました。
ジン法律事務所弁護士法人でも、新生フィナンシャルに対する過払金請求の依頼はよくありますので、ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。