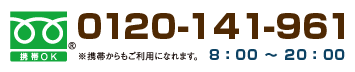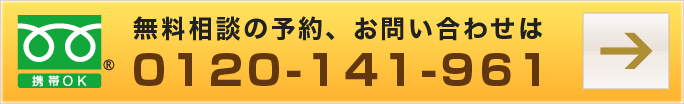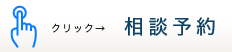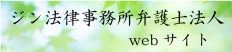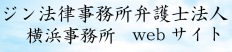オリコ過払い金計算の判決
西都簡易裁判所令和元年11月27日判決
オリコ複数のカード過払金と計算方法
オリコの過払い金計算が争われた西都簡易裁判所令和元年11月27日判決です。
2種の取引が並行していたケースです。
複数のカードで過払い金が発生しているものの、一部のカードは取引終了から10年経っている、というような場合には計算方法によって金額が変わってきます。
事案の概要
原告は、平成12年5月24日契約の□-ンカード「アメニティ」契約(第1取引)とオリコカード契約 (第2取引)により、キャッシングをしていました。
これらの取引について過払い金請求。
オリコは、第2取引について、平成17年に完済しているから、そちらの過払い金について消滅時効を主張。
取引の一連性?
このような時効が主張された場合に、時効期間が過ぎていない取引と一連であると評価されれば、時効の主張は否定、過払い金の請求ができることになります。
この認定については、それぞれの契約時の状況を認定しています。
第1契約を締結する際、勤務先及び勤続年数、利用限度額(本人の希望により20万円)、月々の返済額(1万円ずつ)等を契約申込書に記入。
第2契約を締結する際、勤務先及び勤続年数等を契約申込書に記入し、締結。
これらの経緯等に照らせば、第1契約及び第2契約は、それぞれ契約内容、目的、機能等を異にし、与信審査を経た上、原告、被告間において、借入利率や返済方法について別個に合意しているものといえるとされています。
第1取引及び第2取引は、何れも利息制限法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含んだ別個の基本契約に基づき、継続的に借入とその弁済が繰り返される別個の金銭消費貸借取引であるとみるべきであるから、これらを一連一体の連続した貸付取引であるとみることはできないとされています。
基本契約が異なるということで、残念ながら一連性は否定されています。
併存取引における弁済の意思
第2取引の支払が開始された平成12年10月12日から同取引の終了した平成17年8月12日まで各取引は5年間、併存していました。
第1取引及び第2取引の各支払は、ほぼすべてが同じ日にされているところ、同じ日になされた支払のうち、期限どおりに銀行引落による支払がなされているものについては、第1取引と第2取引に基づく各債務を合算した金額が、同一銀行、名義人の同一口座から一括して支払われていたと認められています。
2種類のカード支払いがまとめて引き落とされていたわけですね。
このような態様で支払を継続していた原告としては、第1取引及び第2取引に基づく各債務を一括して支払う際、毎回の返済が本件ff取引のうちいずれに対する弁済であるのか、取引ごとに支払を区別する意思は希薄で、あえて2個の過払金返還諦求権が併存するといった複数の権利関係が発生するような事態の発生は望まないものと考えられるとしています。
同一の貸主と借主の間で複数の基本契約に基づき併行して取引が繰り返されているような場合、一般に、同一の債権者
に対し数個の債務を負担するような債務者は、借入総額の減少を望むのが通常と目されるとしています。
以上によれば、借主である原告が第1取引及び第2取引に基づく各債務を一括して支払うことにより、第2取引について過払金が発生した場合、この過払金は、当事者間に充当に関する特約が存性するなど特段の事情のない限り、原告は、その当時存在する第1取引の債務への当該過払金の充当を指定したものと推認するのが相当である(平成15年7月18日最高裁判所判決参照)と結論づけています。
借主の意思からして、総債務の減少を希望するのは当然といえるでしょう。
併存型取引の問題は論点をそらされやすいのですが、平成15年最判で明確に述べられている点です。
消滅時効は?
このような前提で、オリコが主張する消滅時効について判断されていきます。
第2取引は第2契約に基づく金銭消費貸借取引であるから、その各弁済金は、当事者間における充当の合意又は弁済の指定がなければ、民法489条及び491条の規定に従って個々の借入金に充当されることになるところ、同取引は金銭の借入と弁済を繰り返している状況にあり、この状況によれば、同取引の開始当初において、金銭の借入と弁済を繰り返すことができること、その借入に対する弁済は、個々の借入金に対して行うものではなく、借入金全体に対して行うことの合意をしていたと認めることができ、この合意は、借入金償務につき利息制限法所定の制限利率を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、その過払金をその後に発堆する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいたと認めることができるとしています。
前提として、取引内の充当合意を認定しているものです。
過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行すると解すべきであるとの原則。
なぜなら、一股に過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当であり、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきで、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当であるからである(平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷判決)と最高裁判決の確認を改めてしています。
そして、第2取引は、利息制限法による引直し計算前の第2契約に基づく債務を完済したことにより、平成17年8月12日に終了していると認められるから、第2取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、同日から進行すると解すべきであるところ、本件において、特段の事情を認めるに足りる証拠はないとしています。
そうすると、第2取引に係る過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、平成17年8月12日であり、同請求権は、同日の経過から既に10年を経過しているので、消滅時効が完成し、時効消滅していると判断しました。
この過払金元金は、平成17年8月12日時点で1万5697円という額でした。
併存取引の過払い金計算方法
本件各取引について引直し計算をするに当たっては、一方の基本契約に基づく取引(第2取引)について過払金が発生した場合、その過払金は他方の基本契約に基づく取引(第1取引)について、当時存在する借入金債務に充当するのが相当であるとしています。
第2取引で発生した過払金は、いずれもその当時存在する第1取引の債務に充当されることとなる計算を採用しています。
これにより、第1取引について、単独で計算した過払い金よりも、第2取引の過払い金が充当され債務が圧縮される分、第1取引の過払い金額は高くなります。
第2取引の過払い金については、消滅時効が認められてしまっていますが、これは、第1取引に充当できなかった分ということになります。
取引の一体性が認められない以上、この併存取引間の充当が、借り主にとっては有利な計算となります。
オリコのような大手クレジット会社の過払い金では、このような計算の方が有利にならないか確認した方が良いケースも多いでしょう。
オリコに対する過払金請求の依頼もありますので、ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。