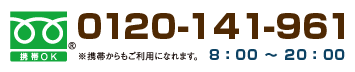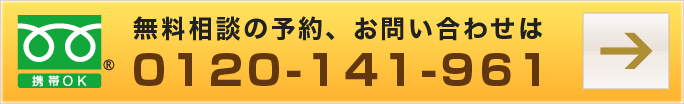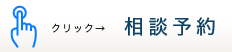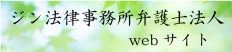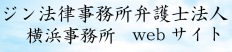ライフ過払い利息の判決
宮崎簡易裁判所令和2年3月17日判決
オリコ複数取引の過払金計算
オリコの複数取引間での過払金充当計算ができるか問題になった事例です。
契約の約款における充当規定や、支払い方法が合算での引き落としであったことなどから、充当計算を認めた裁判例です。
宮崎簡易裁判所令和2年3月17日判決です。
事案の概要
借主である原告は、オリコとの間で2つの取引をしていました。
2003年4月から2008年12月まで「ドライバーズアシスト」という基本契約(取引1-1)に基づく取引。
この契約を変更し6%の利息で組み替えた「お客さまサポートプラン」という契約(取引1-2)に基づき、2009年1月から2018年
12月まで、さらに取引を継続。
これらと並行して2003年4月から2008年2月まで「アメニテイ」という基本契約(取引2)に基づく取引を継続していました。
過払金の計算方法として、並行する別取引への充当が認められるかが争われたものです。
過払金の充当について
取引2で過払金が発生した場合、その当時存在する本件取引1-1の債務に当該過払金が充当されるかという点が争われました。
裁判所は、以下の事実を認定。
本件取引2は、本件取引1-1が開始した18日後である平成15年4月25日から平成20年2月27日まで約5年間、この取引と併存し、この併存期間に、58回返済がされているところ、このうち最後の2回を除く56回は、全て本件取引2の返済日と本件取引1-1の返済日は同一日。
本件契約2においては、宮崎銀行霧島町支店の原告名義の口座が、支払口座とされていました。
本件契約1-1の融資限度額については、同契約の一般条項第4条に「会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は、当社が別に定める利用限度額を超えてはならないものとします。」との記載
がありました。
本件契約2の融資限度額については、同契約の会員規約第6条に「本契約の融資限度額は別途甲が定めた決定融資額の通りとします。」との記載。
本件契約1-1の期限の利益喪失条項については、同契約の一般条項第16条に「本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失」うとの記載がありました。
契約条項における充当規定
被告のカード契約の支払債務の充当順序について、平成8年頃の契約条項には「会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社の適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。」との記載がありました。
令和元年頃の契約条項には「会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づきオリコに対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、オリコの適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。」との記載がありました。
充当に関する借主の意思
上記の事実によれば、本件取引2と本件取引1-1は、原則として、同一口座から同一日に本件契約2に基づく返済金と本件契約1-1に基づく返済金の合計額が自動的に振り替えられていたものと推認され、そうであれば、いずれの取引に対しいくら弁済されたものであるかについて原告の意識は相当に希薄であったと考えられると指摘。
また、本件契約1-1の契約書裏面には契約条項の抜粋しか記載されておらず、支払債務の充当順序に関する契約条項は見当たらないが、上記の事実及び弁論の全趣旨からは、上記条項と同様、他の契約の債務に充当できる旨の条項が本件契約1-1にも定められていたと強く推認され、これに加えて上記のとおり融資限度額や期限の利益の喪失においても
他の契約と相互に関連していることを踏まえると、上記各取引は、密接な相互関連性が認められるとしています。
さらに、借主である原告は、弁済の際、債務総額の減少を望み、本件取引2の過払金と本件取引1-1に係る債務が併存するような事態が発生することを望まなかったものと考えられると言及。
以上によれば、本件取引2に係る債務の返済の際、制限超過分を元本に充当した結果、既に同取引に係る貸金債務が完済されて存在しなくなるか、又は債務が存在する額を超えて弁済することになる場合には、原告は、本件取引2の過払金に
ついて、弁済当時存在する本件取引1-1に係る債務への充当を指定したものと認めるのが、合理的意思解釈として相当であるとしました。
基本契約が別でも
本件取引1-1と本件取引2は、異なる基本契約に基づく別個の取引である、あるいは、事実上1個の連続した取引とみることができないものであるとしても、上記判断は左右されないとしています。
このように解することは、過払金に対する利息の利率よりも借入金に対する約定利率の方が高いことに鑑みれば公平の原則にも適うところであり、また、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする利息制限法の立法趣旨にも合致するものと考えられるとしました。
そうすると、本件取引1ー1と本件取引2を個別に引直し計算を行った結果、本件取引2で過払金が発生する場合には、その当時存在する本件取引1-1の債務に当該過払金が充当されることになると結論づけました。
一連の取引として引直し計算すべきか
オリコは取引の一部について変更契約をしていたため、その前後で一連計算をして良いかが争われました。
裁判所は一連計算を採用。
原告と被告は、平成21年1月7日、本件契約1-1に係る平成20年12月24日現在の残債務が50万2024円(元本49万5449円、未収利息・手数料6575円)であることを確認した上で、利息を年率6%に変更して残債務の支払方法を、月額7000円(ただし、最終回のみ721円)、90回払いの元利均等分割返済に変更し、その他の事項は、原契約の各約定が適用されることを内容とする本件契約1-2を締結していました。
本件契約1-2は、本件契約1ー1の約定利率や月々の返済額などの支払条件を変更したものにすぎず、本件契約1-1に基づく残債務の返済について引直し計算をする場合には、本件取引1-1と本件取引1-2は一連の取引として引直し計算をするのが相当としました。
オリコによる錯誤無効の主張
さらに、被告であるオリコは、変更契約について錯誤無効を主張したため、この点も検討されました。
被告は、この引直し計算をする場合、本件取引1-2に係る本件契約1-2は錯誤無効であるから、本件取引1-2についての約定利率は年6%ではなく年18%で計算すべき旨主張するが、本件契約1-2を締結する際に被告が原告から過払金の返還を求められることはなく、残債務額が引直し計算によって減額されることはないと思っていたとしても、それは将来の不確実な事実に対する期待ないし願望にすぎず、動機の錯誤には当たらないとしました。
また、被告は、原告が返済困難であったことについて錯誤があった旨の主張もしているが、これを認めるに足る証拠はないとして排斥。
したがって、本件取引1-1と本件取引1-2は一連の取引として引直し計算(ただし、本件取引1-2部分についての約定利率は年6%で計算)すべきことになるとしました。
悪意の受益者
貸金業者が制限超過分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定されるものというべきである、と最高裁の論理を展開。
しかるに、被告は、特段の事情について何ら主張立証をしていない、よって、被告は、悪意の受益者と認められるとしました。
オリコに対する過払金請求の依頼もありますので、ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。