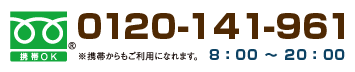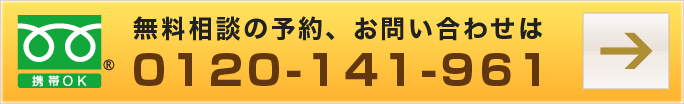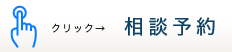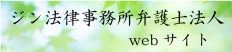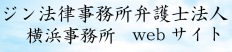エイワ過払金の判決
横浜地方裁判所2021年7月20日判決判決
エイワ過払い金回収しすぎた後に自己破産
過払い金の請求をして回収したものの、裁判所の判断が変わり、過払い金の金額が変わることもあります。
そのような場合に、回収した過払い金を返さなければならないのか、自己破産との関係で問題になった事例があります。
横浜地方裁判所2021年(令和3年)7月20日判決(消費者法ニュース130号)、東京高裁2022年1月12日判決です。
回収しすぎた過払い金が自己破産の免責対象になるか問題になった事例です。
エイワ過払い金の減額
最初は、借主が原告となってエイワに対して過払い金の返還請求をしました。
過払い金の裁判を起こしています。
第一審の簡易裁判所では、過払い金の請求が認められました。判決には、仮執行宣言が付されていました。
これは判決確定前でも差し押さえができるものです。
そこで、借主は、仮執行宣言つき判決に基づいて動産の差し押さえにより42万0112円を回収。
しかし、エイワは控訴しました。控訴した際に、仮執行宣言の効力を止めることもできるのですが、それはしませんでした。
控訴審の地方裁判所では、第一審判決を変更して過払い金の認容額を減額する判決を言い渡しました。
この判決が確定。
そうすると、借主は過払い金を回収しすぎていることになります。
エイワは、借主に対し、払いすぎた過払い金について、不当利得返還請求権を持ちます。
過払い金回収後の自己破産
ところが、借主は、自己破産をしました。
エイワの請求に対し、借主は自己破産による免責許可決定が出され、支払義務はなくなっていると主張。
ここで、このエイワの請求権がどうなるか争われました。
自己破産の免責許可の対象になり、他の借金と同じく支払い義務がなくなるのか、それともエイワに返さなければならないのかが争われたわけです。
債権者一覧表にもエイワを記載
裁判所は、まず、以下の事実確認をしています。
エイワと被告との間の平成20年3月3日から平成21年12月18日までの金銭消費貸借取引にかかる不当利得返還請求権の存否及びその内容が争われていたのであり、本件第一審判決について双方から控訴がされ、同事件が地方裁判所に係属中に被告は破産手続開始決定を受けたのであるから、同裁判所の判決のいかんによっては、本件第一審判決に基づいて被告が回収した金額と本件控訴審判決による金額の差額について、エイワが不当利得返還請求権を取得するに至る可能性があることは、本件破産手続開始決定がされた時点において当然に予測されたものであり、そのため、被告は、破産手続開始申立書の債権者一覧表にエイワを登載し、報告書においてもその事情を説明していたものであると事実認定しています。
流れとして、一審判決・差し押さえによる回収、控訴審で争い、その途中で自己破産の申立、エイワの請求権についても、念のため債権者一覧表に記載し、破産裁判所に対する報告書で事情説明というものです。
自己破産では、債権者一覧表に債務を記載して申立をします。そこにエイワも債権者として記載していたものです。
エイワは、自己破産手続を認識していたことになります。
裁判所はエイワの請求を否定
かかる経緯からすれば、エイワの本訴不当利得返還請求権が、「破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破産法2条5項)として破産債権であることは明らかであるとしました。
エイワは、破産手続において本訴不当利得返還請求権を行使することが不可能であったから、同請求権は破産債権ではないと主張。
しかし、被告に対しては、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がされているから、手続上、エイワが上記請求
権を行使する余地はなかったものであると指摘。
かかる事情をもって、エイワの本訴不当利得返還請求権が破産債権ではなかったなどということはできないとしました。
同時廃止と管財手続とは
破産手続きでは、簡単に終わらせる同時廃止手続と、破産管財人が選任される管財手続があります。後者の管財手続では、債権届を提出する手続がとられることもあり、この場合には、配当を受けられることがあります。
しかし、財産がないような場合には、管財手続にせず、簡単に同時廃止で終わらせることになります。今回の破産手続は同時廃止だったので、そもそも、債権届の提出など、債権を行使する機会がなかったことを指摘しています。
エイワの過払い金が自己破産申立て費用に
エイワは、被告が本件第一審判決に基づいて回収を図る一方で、回収した金員を破産手続開始申立関係費用に充てたことが不当であると主張。
しかし、被告は、言い渡された本件第一審判決に基づいて適法に権利を行使したにすぎず、後日、同判決を変更する本件控訴審判決が言い渡されるに至ったとしても、被告が控訴審において言い渡される判決の内容を事前に知りながら、あえて本件第一審判決に基づく強制執行をしたなどの事実を窺わせる証拠はないとしました。
以上によれば、本訴不当利得返還請求権は免責されたものであると判断しています。
仮執行宣言というのは、こういう制度なので、この判断は妥当でしょう。
仮執行宣言を避けたければ、その制度を利用しておくべきだったといえます。
自己破産の対象になる債権
自己破産で免責許可の対象になる債権は、「破産手続開始前の原因に基づいて生じた」(破産法2条5項)ものである必要があります。
この解釈については、破産債権の発生原因のすべてが備わっていなければならないとする全部具備説と、主たる発生原因だけが備わっていれば良いとする一部具備説があります。
書籍などでは、一部具備説が妥当とされています。今回の判決もこれを前提としています。
エイワの主張は、おそらく全部具備説に従い、まだ判決が確定していなかったから破産債権にならないという主張だったものと思われますが、排斥されたという流れです。
東京高裁もエイワ主張を否定
エイワは横浜地方裁判所の判断に対し控訴しました。
しかし、東京高裁令和4年1月12日判決でも、不当利得返還請求権の主たる発生原因は動産執行であることを示し、これが破産手続開始決定前にされていることから、不当利得返還請求権は破産債権になるとしています。
過払金のご相談は以下のボタンよりお申し込み下さい。