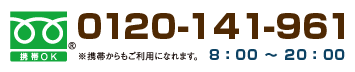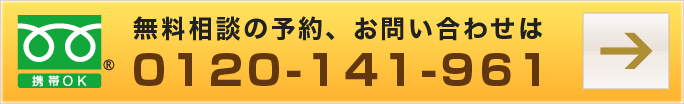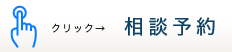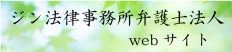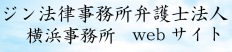包括契約論
消滅時効に対する主張・包括契約論
消滅時効の主張
過払い金の裁判では、貸金業者側から、「過払い金は消滅時効にかかっているから、請求できない」という主張がされることがあります。
過払い金を返せ、という権利が、不当利得返還請求権だとすると、民法167条1項に「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 」と書いてありますので、10年間で時効にかかるという主張がされるわけです。
具体的な場面としては

基本契約などが2つに分断されるとの主張がされ、最初の基本契約の完済により過払い金が発生しているが、分断されるため、2つ目の基本契約には充当されない、1つ目の基本契約が終了してから10年経過しているため、時効である、という主張がされることがあります。
基本契約は終了しているのか?
このような時効の主張に対して、まず、そもそも1つ目の基本契約は終了しているのか?というところに疑問を投げかけなければいけません。

基本契約が終了していないなら、基本契約内の充当という話になります。
貸金業者は、単に、「借金が完済されたから基本契約は終了した」と主張してくることがありますが、そもそも解約手続自体があったのか、解約手続があったとして、終了したと言い切って良いのか、疑問を持ちましょう。
包括契約論
このような疑問をさらに突き進めると、そもそも、基本契約って何なの?という話になります。
平成20年12月28日時点で、最高裁は、基本契約を明確に定義していないと思います。
業者が主張している基本契約よりも、広い概念で包んでしまおうというのが包括契約論です。

基本契約の概念を広く考えれば、全体を一つの契約と見ることができます。そして、包括契約の特徴としては、継続的な契約であること、利息制限法を上回る利率で貸付がされていることというものが挙げられます。その特徴を踏まえると、単に借金がなくなったとしても、過払い金の返還がされていなければ、契約は残っていると考えるのです。
詳しい理論構成などは、こちらの本に書かれています。