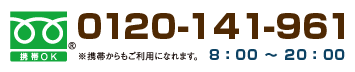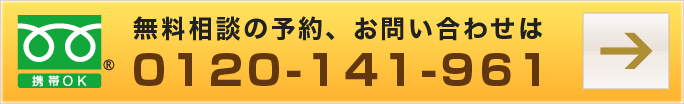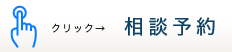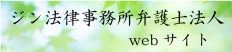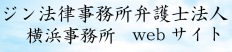社債と利息制限法の判決
最高裁令和3年1月26日判決
社債に利息制限法が適用されるのか
社債に利息制限法が適用されるのかの争点について、最高裁の判決が出たので紹介します。
結論としては、否定されています。
動画での解説はこちら
利息制限法は過払い金の根拠法
利息制限法という法律は、お金を貸しているときに、利息を取り過ぎていはいけませんと規制している法律です。
高すぎる利息は無効になるという法律です。
元金が100万円を上回るようなケースだと、年利では15%が上限。
元金が10万~100万円のケースでは、年利18%が上限。
元金が10万円までは年利20%が上限と規制されています。
過払い金の仕組み
この上限利率よりも高い利息を払っているという場合には、払い過ぎている部分が借金の元金に当てられます。
元金がなくなっても、払っている部分があると過払い金となり返還請求ができるのです。
消費者金融、サラ金や信販会社の昔の借金だと、この上限利率を大きく上回っていたので、この利息制限法によって過払い金の請求ができたのです。
社債とは会社の債務
社債は、会社が発行する債券。
お金を借りるための一つの方法で、会社法で細かい規定がある制度です。
社債発行手続きには複数の種類がありますが、一定の手続きを踏んで会社が一般的に広くお金を集める手法とされます。
上場会社が証券会社を通じて社債を発行するケースもあります。ソフトバンクが個人向け社債を発行したりしています。
社債は、期間経過後に返還する形になるので、借金のようなものといえます。
また、一定金額の利息のようなものを発行条件にすることもできます。
そこで、このような社債で、利息が高すぎる場合に、利息制限法が適用されるのかどうか争われたのです。
事案の概要
今回の社債発行会社は、破産をした会社です。
破産をしてしまった投資システム会社がありました。
そこと社債取引をしていた人がいました。
この社債の利息が非常に高かったというもの。
この社債が何回も発行されていて、なかには年利90%のものも。
その会社が破産をしたので、裁判所で破産管財人が選任。
破産管財人は、破産会社の財産を回収しなければいけないということで、この高い利息が、消費者金融等の取引と同じように過払い金請求ができるものと判断して提訴したものです。
利息制限法の適用主体は法人も
この利息制限法という法律は、法人でも適用はされます。
消費者問題でよく出てくる消費者契約法は法人には適用はされないとの規制があります。
これに対し、この利息制限法は、主体には制限がありません。
法人も過払い金の請求はできます。
昔は、事業用ローン、商工ローンなどに対して、法人が過払い金請求をする事例も多くありました。
また、利息制限法は、貸主にも、特に制限がありません。
貸主が個人でも適用されます。
つまり、個人間取引、個人間融資でも利息制限法は適用されます。
個人間だから、という理由で、年利15%、18%などの制限を上回るような利息を設定すると、完済後に過払い金請求を受ける可能性があります。
個人間融資でも、さらに利息が高くなると、出資法違反で刑事罰の対象になりますので、ご注意ください。
高等裁判所までの判断
一審の東京地裁は、社債への利息制限法の適用を否定。
別記事でも紹介しています。
破産管財人の請求を棄却。
続く、東京高等裁判所も、東京地方裁判所の判断を尊重。
単純に、利息制限法の適用はないという判断をしました。
そして、今回の最高裁判決へ。
最高裁判所の判断
最判令和3年1月26日です。
結論としては、上告を棄却。
破産管財人の主張を認めず、社債には利息制限法の適用がないという結論でした。
社債と貸金の類似点、相違点
利息制限法1条は、「金銭を目的とする消費貸借」における利息の制限について規定しているところ、社債は、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であり(同法2条23号)、社債権者が社債の発行会社に一定の額の金銭を払い込むと償還日に当該会社から一定の額の金銭の償還を受けることができ、利息について定めることもできるなどの点においては、一般の金銭消費貸借における貸金債権と類似すると指摘。
しかし、社債は、会社が募集事項を定め、会社法679条所定の場合を除き、原則として引受けの申込みをしようとする者に対してこれを通知し、申込みをした者の中から割当てを受ける者等を定めることにより成立するものであると指摘。
このように社債の成立までの手続は法定されている上、会社が定める募集事項の「払込金額」と「募集社債の金額」とが一致する必要はなく、償還されるべき社債の金額が払込金額を下回る定めをすることも許されると解されるなどの点において、社債と一般の金銭消費貸借における貸金債権との間には相違があると指摘。
利息制限法の趣旨の借主保護
また、社債は、同法のみならず、金融商品取引法2条1項に規定する有価証券として同法の規制に服することにより、その公正な発行等を図るための措置が講じられていると相違点を指摘。
ところで、利息は本来当事者間の契約によって自由に定められるべきものであるが、利息制限法は、主として経済的弱者である債務者の窮迫に乗じて不当な高利の貸付けが行われることを防止する趣旨から、利息の契約を制限したものと解されるとしています。
社債については、発行会社が、事業資金を調達するため、必要とする資金の規模やその信用力等を勘案し、自らの経営判断として、募集事項を定め、引受けの申込みをしようとする者を募集することが想定されているのであるから、上記のような同法の趣旨が直ちに当てはまるものではないとしました。
今日、様々な商品設計の下に多種多様な社債が発行され、会社の資金調達に重要な役割を果たしていることに鑑みると、このような社債の利息を同法1条によって制限することは、かえって会社法が会社の円滑な資金調達手段として社債制度を設けた趣旨に反することとなるとしています。
例外としての特段の事情
もっとも、債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し、社債の発行に仮託して、不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど、社債の発行の目的、募集事項の内容、その決定の経緯等に照らし、当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合には、このような社債制度の利用の仕方は会社法が予定しているものではないというべきであり、むしろ、上記で述べたとおりの利息制限法の趣旨が妥当するとしました。
そうすると、上記特段の事情がある場合を除き、社債には利息制限法1条の規定は適用されないと解するのが相当としました。
本件において上記特段の事情の存在はうかがわれないので、本件社債に利息制限法1条の規定は適用されないとして、破産管財人の主張を排斥したものです。
破産会社からお金が流出するリスク
本件で気になるのは、社債発行会社が破産していることです。
破産管財人として何十件もの事件を取り扱っていますが、末期症状の破産会社からお金が流出することはよくあります。
社長の家族や関連会社にお金が流れている場合には、否認権の行使など破産管財人はお金の取り戻しを検討します。
社債とはいえ、203回の発行が1名、年利90%となると、怪しい印象を受けます。
管財人が最高裁まで争ったのも、このような印象を受けたのではないでしょうか。
このような事件の場合には、特段の事情でフォローするというのが最高裁のスタンスのようです。
特段の事情があれば利息制限法の適用もありうる、過払い金も請求できるという立場です。
ただ、最高裁判所がこのように特段の事情という場合、立証のハードルはめちゃくちゃ高いです・・・。
くれぐれも悪用されないことを願っています。
経営者の皆様が、高利の社債取引を持ちかけることがあるかもしれませんので、ご注意ください。
過払金のご相談は以下のボタンよりお申し込み下さい。